
D軽費老人ホームを辞めた後
なかなか在職中は時間を割くことができなかったですから、今時間が十分にある状態はある意味自分にとって、宿題になっていた「発達障害の克服・軽減」ことを取り組むことのできる、貴重な時間だなと感じていました。自分の今後の人生を左右する大事な時間です。発達障害の軽減・克服の見通しが立たなければ、再就職はしないと決めました。
自分のことを低スペックのパソコンと感じることがあります。他の人と比べて能力が低いなと思いますよ。他の人が当然できるようなことができないですから。
「低スペッパソコンで、デフォルトではその能力がないのであれば、専用のソフトを脳にインストールすればいい」そういう発想で取り組んできました。足りないなら入れればいいのです。低スペックパソコンだろうが、そんなの関係ないですよ。
私の発達障害のアプローチの仕方は大きく分けて3種類でした。
①効率化の仕組み
②認知・知覚の仕組み
③メンタル強化の仕組み
これらになりますね。他の人に比べてできない事が多いのであればその仕組みを作ろう。こういうことでした。これが「頭の中にそのソフト入れる」という事です。
この時期には①番と③の仕組みを構築していました。 ②に関しては、五里霧中でしたね。
まったくもってきっかけすらない。
③番は、「100回忌CD」を徹底的に学ぶことになります。自分の中ではこれを行うことで自分が良くなる事を確信していましたね。自分の中では重要だと思っていました。執着していたといってもいいでしょう。具体的に言うと、まだ、「100回聞きCD 」の文字おこしと「すること・しないこと」の抜き出しをしていました。
そしてフラッシュバック

辞めてから1ヶ月後位から、フラッシュバックが強くなりましたね、ある特定に人物がでてくるのです。T主任ではないです。仮にKさんとしておきます。なぜKさんが出てくるのかわからない。正直困りました。
ほぼ同時期にD事業所に入社をした方で、普通にいろんな話をして、それなりに仲の良かった人です。非常に女らしい女性ですが、いろんな部分がグラグラしている。と感じていました。
ほぼ初対面で、自分の身の上話、精神的に参っていたこと、旦那さんのことなど。話を聞いてくれる人なら誰でもいいタイプでしたね。非常に依存心が強い人という印象です。
辞める前の1年ほど前から、私に対して馬鹿にし、露骨に無視をすることがありまして、彼女なりに私に対して何か思うことがあるんでしょう。理由は判らないですし、多分話し合えば解決するだろうと思っていましたが、多分T主任のネガティブキャンペーンの影響があるのだろうと思っていました。ですから関係改善の必要性は感じなかったですね。人間関係は相互作用です。ようするに私が揺るがなかったら、相手は空回りしますので、結局元に戻るのです。そう考えると一過性のものといえると思います。むしろ「修行」です。
と思っていたのですがね(笑)。なぜKさんがフラッシュバックでやってくる。そして私を責めるのです。今までのフラッシュバックの中で、いちばん強烈なものですね。こんなに追い込まれたことはなかった。瘴気とともに現われて、しかもリアル過ぎます。さすがに24時間フルにいるわけではないですが、いつくるかわからないのも辛いですよ。
出てくると、「やはり自分が悪いのではないのだろうか?」と考えてしまうのです。解決策がない堂々巡りに陥っていました。自分が悪いではないという思いは、最終的には「自分なんて生きている価値がない」という考えになります。非常にまずい状況です。
フラッシュバックをある程度克服したと思ったら、今までで最強のフラッシュバックが来ました(笑)。
そんな中で私を支えていたのは、やはり斎藤一人さんの教えです。そして、「100回聞きCD」のまとめを終われば、このことが解決できると確信していました。根拠はないのですけどね。苦しみながらも、それでも少しずつ前進はしていたかな。
成果物系「仕組み 効率化」
介護職でした①

いろんな弱点を抱えていても、どうやって仕事をするかとして日常生活を送るか。
これが私のテーマでした。介護職を辞めてから一応の完成、ということが自分の中では少し悲しいポイントですがね。でも仕事を辞めなければ完成はしてなかったね。なるようになっているとそう思います。
私の仕事は入所施設の現場の介護職でした。この仕事の中で起きることにどうやって対応するか。いろんなことが人と違うので、工夫をしなければやっていけないですね、漫然と仕事することは出来ないね。これが現実でした。
仕事の特徴として、屋内であること。基本的に時間内で終わる職場でした。あまり残業はなかったです。日常で行う業務というのは基本的に決まっています。その曜日によってとか、例えば何かの行事があるかとか、そういう違いはありますけども、基本的にルーティンワークの仕事です。
突発的な出来事、これはどんな職種で起きることなのだと思います。ただ、介護の業務の範囲内での突発的な出来事です。例えば入居者様の状態が悪化したとか。ただ、経費老人ホームなので、そんなに要介護度の重い方はそれほど多くはないです。あまり状態の良くない利用者様は病院へ転院されるので、それほど殺伐とした雰囲気ではないです。特別養護老人ホームを経験していますので、比較すると入所施設の中でもハードな職場ではないといえます。基本的に 肉体労働です。記録を書くというのもありますが。メインの業務は入居者様のケアです。
介護職でした②

上記では介護職の魅力が伝わらないな。確かに賃金は高いわけではないです。業務内容は夜勤があるところだと、その現場によってだいぶ差があるので一概にはいえませんが、やはり大変ですね。利用様や職員との人間関係で悩む職員も多分多いでしょう。だからといってこの仕事に魅力がないわけではないですね。
その会社に長くとどまる人がいます。簡単に辞める人も多いなかで、なぜなのか?長くいる人は、結局のところその業務に耐えていける人なのです。
長年介護職に関わっていて、介護に向いている人というのは分かってきました。利用者様に受け入れること。これが1番です。利用者様が嫌がる人は結局、長くいられないですね。そういうことなのでした。利用様の為にという行動も、利用者様本人に受け入れてくれなければ意味がないです。これが1番大きいです。基本的に介護チームプレですね。能力的に多少の差異があっても、カバーできてしまうのです。個人的な能力というものに程大きなウェイトを占めてはいない仕事です。
どういう人が受け入れられるか。長持ちする人はどういう人なのか、ずっとそばにいられる人はどういう人なのか。それは情緒が安定している人です。間違いなくストレスのかかる仕事なのですが、ストレスを覚えていても引きずらない。自分の顔出さない。こういう人を高齢者は受け入れます。
特別に際立った個性とか必要ないです。逆に相手インパクト与えることは正直あまり好ましくはないです。重要なことは、自分の心に芽生えてくるネガティブな感情を処理する作業が必要です。他の職種よりも求められると思います。これが上手くこなせないと、利用者は気がつきます。例え認知症の利用者であっても、です。こういう心の修行ができること、わたしにとっての「魅力」です。
こういう仕事環境の中で徹底的に効率化を目指します。そして道具を使う言うことに拘ります。人間の能力というのは正直そんなに差はないです。当事者の私が言うと驚く方もいると思いますが、当事者の感想としてはそういうことですね。人間の能力差というものは正直それほど大きいと思えないですね。であるならば、それを補完する意味で道具を使えば良い。それが持たざる者としての選択でしたね。
用意するもの
<IT機器類>
ノートパソコン
ドキュメントスキャナ
テプラ
プリンター
スマートフォン
裁断機
<ソフト系>
Google系サービス(各種検索、メール、カレンダーは必須)
マインドマップ系ソフト(私はFreeMindとMindmeisterを使用しています)
Ever note
タスク管理ソフト(私はtoodledo、nozbeを目的に分けて併用してます)。
クラウドストレージサービス(私はgoogledriveです。Dropboxも検討中です)。
メインは以上ですね。目的別に他にもいろいろ使っています。
紙について①

基本的にペーパーレスを目指します。私はこれまでの人生で物を片付けることが出来ない人でした。はっきり言ってごみ屋敷の住人ですね。学校でもプリントの提出がありますよね?自分では提出で出来たことがなかったと思います。よく、高校を卒業できたと自分でも信じられない思いですね。学校側が「面倒くさいから卒業させちゃえ」というノリだったら面白いね(笑)。
社会人になってもその傾向がありましたよ。小さい頃と基本的に何も変わっていないですから。たださすがにそんなことをしていると、すぐクビになってしますので、重要な種類や提出しなければならないものは、自分では管理しませんね。親に預かって貰っていました。
なぜかというと、ゴミの中に埋まってしまうので。何層にも堆積しているのです。一度埋まってしまったら発掘はまず無理ですね。いやいや、さすがに片付けようとは何度も試みましたよ。でも1週間もたないのですね。最終的には何もしなくなりますね。当事者あるあるかな。
さてゴミ屋敷の住人として一番困るのが「紙」の扱いなのでした。普段生活していると結構紙は溜まります。領収書とかね、道を歩けばちょっとしたとか広告とか。訳がわからないダイレクトメールとかね。世界は紙に満ちあふれている。仕事でもそうなのです。ちょっとした企画書とか、回ってきたちょっとした紙、使うかどうか判然としない書類が結構ありますもんね。
重要な保証書、例えば資格の証明書とか、契約書とか、多分原本を取っておいた方がよいと思う書類がありますけども、それ以外の書類のほうが圧倒的に多いわけですよ。これをドキュメントスキャナを使ってパソコンに取り込みます。そして取り込んだ後の紙は原則破棄なのです。残していても仕方がないので。必要とあればプリントアウトすればいいのです。
紙について②

さて続きまして。パソコンに取り込んだ情報をどうするか。です。
evernoteというもの使います。第2の脳と言われるクラウドサービスですね。ここが最終的な情報の保管庫になります。フォルダとタグで管理をすることになるのですが、検索機能がついているので、evernoteにいれた情報なら探せないことはないのですね。これは助かりますよ。書類の管理で困るのが、どこに仕舞ったか判らなくてとりだせないことですから。この心配がなくなるとことは、これは整理整頓が苦手な当事者の方には非常に大きなことです。
続きまして本ですね。電子書籍がだんだんふえてきていますが、まだまだ紙媒体の本を購入することや、本棚にたくさん本のある方も多いと思います。本棚も結構スペースを取りますし、また本棚自体には未整理してない紙やゴミがよく判らないものが陳列しますね。私にとって本棚はハッキリ言って敵です。
これも最終的にはクラウドサービスで管理します。その前に「自炊」をします(ご飯系のことではないです)裁断機で背表紙を裁断して、本を解体するのです、バラ状の紙にして、ドキュメントスキャナでパソコンに取り込みます。こうすることで本と本棚が部屋からなくなるのです。それでも、例えば資格試験の問題集など、本でのほうが利用しやすいものが残ると思いますが、小ぶりのカラーボックスぐらいで多分収まるでしょう
机の上
<書類系>
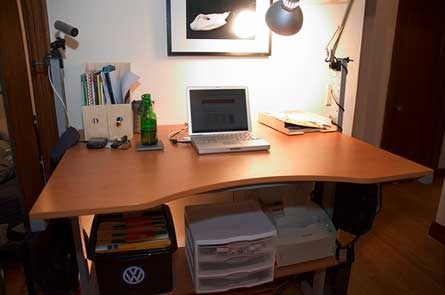
いろんな作業する机、結構無駄な書類とかありませんか?基本的に机の上はペーパーフリーが望ましいと思います。ただ現実問題として現在作業中の仕事でどうしても紙を使わざるをえないことがあると思います。
そういう場合は置き方に工夫をします。縦置きで管理するのです。絶対横置きはだめです。あくまで視覚的に判りやすく、が基本です。横置きはやっぱり見づらいですよ。書類ですが、100円ショップで購入した縦置きファイルボックスに色分け現在4種類です。
当然ファイルにもタグ付けもします。締め切りが決まっているものは手前側に置いてください。
赤色ファイルボックス 締切日が決まっていて重要度が高いもの
黒色ファイルボックス 締切日が決まっていて重要度が低いもの
青色ファイルボックス 締切日が決まっていなくて重要度が高いもの
緑色ファイルボックス 締切日が決まっていなくて重要度が低いもの
<文房具系>
文房具についても必要なものだけおきます。とりやすい配置にして、基本的に文房具類も縦置きですね。配置は固定です。そのためには文房具入れに、それぞれインデックスシールやテプラで必ずタグをつけます。タグは重要ですよ。基本的に記憶はあやふやなもので、毎日使っていても「あれ、これどこだっけ」と思うこともありますから。ものを考える時間さえ無意味ですね。
部屋の整理整頓

次に衣類関係の整理です。基本的にクローゼットで吊るして管理しています。視覚的に判りやすく、を心がけます。箪笥は下着だけですね。さて、タグをつけます。ハンガーに例えば、ズボン類、アウターとかテプラで作ったシールを貼るのです。こうすることで「この服はどこにしまうのだっけ?」といった無駄に探すことや考える時間がなくなります。私は服をハンガーにかけることすら非常に困難な人間でした。どこにかければいいか混乱するのです。ただ、ちょっとの工夫で劇的に改善しました。
CD DVD等も外付けハードディスクでの管理が基本です。現物は破棄かどうしてもとって起きたい場合はダンボールにいれて押入れにしまいます。わざわざ目に付く所に置く必要はないですねここまですると見違えるように部屋が綺麗になっていると思います。精神衛生にも非常にいいですね。
「タスク」についての基本的な考え方

「タスク」平たく言えばする事ですね。「なんだ、そんなことか」といわれる方もいるかもしれませんが、これは徹底して行えば、たぶん人生が変わるのではないかと思います。行うべきことが明確にわかるし、予定にいかなければ、なぜ駄目だったかという振り返りもできます。人によっては壁にかけているカレンダーやスケジュール帳でこなしている人も多いかもしれません。
なかなか、手順が混乱してしまうということはありますよね。私もそうでした。何をしていいか分からない。これを解決する方法があります。私はタスク管理にクラウドサービスを使っています。これによりパソコンとスマートフォンで効率的にいつでもアクセスできるのです。そして「タスク」2つに分けて考えています。
<タスクの管理>
nozbeというクラウドサービスを使っています
基本的に、「プロジェクト」と言う考え方をします。完了までに2日以上かかるもので、タスクが複数あるものです。
たとえば1ヶ月後の納期に間に合わせなくてはいけない仕事があるとします。このためには様々なアクションが必要となります。例えば、田中さんにこの書類の作成を頼まなくてはいけない。部下の木下君に指示を出さなくてもいけない。これらがタスクとなります。1つのプロジェクトの中にたくさんタスクが必要になる。状況によっては練り直してタスクの変更を起こしなくてはいけない。こういうことのタスクの管理です。
<タスクの実行>
toodledoと言うクラウドサービスを使っています。
「プロジェクト」で管理している今日行うタスクと、「プロジェクト」以外の今日行うタスクを実行するためのツールです。Nozbeを使ったタスクの管理とは別の発想のものです。
基本的に今日行うタスクを表示させるのです。それを順番にこなしていく。そういう使い方をします。非常に高機能なツールなのです。今日のタスクの表示だけでも、さまざまな方法があります。設定も必要になりますが、たとえば2時間毎に分けることや、場所やその仕事に関わる人とかちょっとしたタグで表示することもできます。
<ルーティンワーク>
ルーティンワークということの重要性を感じて仕事をしてきました。特に施設の介護職員の業務9割以上はルーティンワークの仕事です。このルーティンワークということを結構おろそかにしていると人って多いですよ。例えば、毎月の10日やること、3ケ月の毎の第二火曜日にやること、とかを自分の業務の中だけでも明確に把握している人は少なかったです。
このルーティンワークの管理はtoodledoで行います(基本は「タスクの実行」ですが)。
こちらはリピート機能が充実しているので、ほぼありとあらゆる設定ができます。一般の勤め人のかたであれば充分だと思います。これによりルーティンワークのタスクを覚える必要性がなくなる訳です。Toodledoを見ればいいです。そして様々な表示法が出来ますから。この時間にやることは何かとか、この場所でやることは何だろうといった把握ができるのです。そして重要な仕事だから、ルーティンワークになっているのです。Toodledoを使うことで視覚的に把握が出来ますので、まずルーティンワークをこなした後で行うしごとも容易に組み立てることが可能になります。
知識・技能「クラウドワークス」

道具や仕組みを構築することで自分の出来ることを少しずつ広げていました。ですがやはり苦手なこと・出来ないことはやはりあります。無理なものは無理ですから。私は自分の能力に過度の期待はしていません。であるならば自分の苦手な分野をどうするか。1つの答えがクラウドソーシングを利用するということです。
クラウドワークスというサービスがあります。インターネットの職業のマッチングサイトですね。もちろん依頼することも探すこともできます。内容は多岐にわたります。
Wikipediaより
クラウドワークス(Crowdworks)は、株式会社クラウドワークスが運営するエンジニア・クリエイターのクラウドソーシングサイト。2011年に会社が設立され、2012年3月にクローズドβ版のサービスを開始した。クラウドワークスは、エンジニアやウェブデザイナーに特化したクラウドソーシングサービスで、非対面のまま仕事のマッチングから業務の遂行、報酬の支払いまでを一括で行うことができる。サービスの特徴は、時間単位で仕事の受発注ができる「時給制」と、プロジェクト単位で受発注できる「固定報酬制」の2つの方式を採用していること。また、利用に関する手数料は仕事をした報酬額に応じて受注者が負担する仕組みとなっており、発注する側は有料オプションを除き無料で利用ができる。
仕事を探すことも依頼することも、日本全国が市場になる訳です。強烈な競争原理が働くし価格破壊も起きていますね。リアルでならば価格が高くてなかなか外注できない案件も依頼できるのです。斎藤一人さんのCDの文字お越しは、早い段階に一人で行うのは無理だと判断していたのですが、なかなか外注できなかったです。値段が高くて無理だったのですが、クラウドワークスによって可能になりました。わたしで限っていえば、1/3の値段ですみました。まちがいなく外注の敷居は低くなりましたね。すごい時代だね(笑)。
知識・技能「活かそう!発達障害脳」
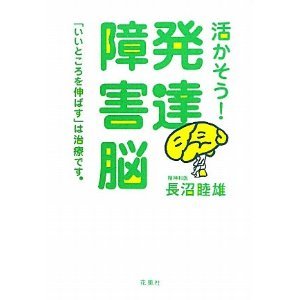
著者は長沼睦雄さんという方です、北海道音更町北海道緑ヶ丘病院勤務。
発達障害の治療の現場に立つ医師と出版社の方の対談形式の本です。脳科学の見地から発達障害について語られているのです。
まず長沼先生の発達障害の考え方は高次脳機能障害であるとのこと。
緑字引用
物理的な損傷という意味ではなく、脳へのダメージをお腹の中の成長過程で受け、その後の脳・心・身体の発達が何かしら阻害されたことで脳の発達アンバランスが生まれたというのが僕の持っている発達障がい観です。高次脳機能障がいというと昔は脳の皮質の問題だと思われていました。すなわち、影響を受けるのは認知だけだと思われていました。けれどもそうじゃないことがわかってきました。注意力も社会性も、記憶の仕方も情緒も混乱するし、おまけに身体までも不器用になったりします。
治療方針は「いいところを活かす」ということです。でこれを聞いた出版社の方とのやりとりが非常に面白いです
緑字引用
う〜ん、「いいところを活かしましょう」ってよく特別支援教育に熱心な先生とかおっしゃいますが、それがイコール「苦手なことはやらなくていい」というスローガンっぽく感じてしまって、すんなりとは賛同できないところがあるんです、正直言って。だって、苦手なことを完全にやらなくていい人生はないと思うし
実を言うと私も同じこと考えました。私の対応策は仕事をする上で自分に弱点であるものをいかに克服するかというスタンスでしたので。ただ本を読んでいくとその考え方がよくわかりました脳に凹凸があり。引っ込んでいるところがあるのであれば、比較的優秀なところがある。そこを活すこことで成長を促すということのようです。発達障害でも脳は成長することを確信している。ものすごく勇気を得られます。現状がどうであれ、変えることは可能なのです。
全編通して、脳についての情報があります。人間の行動や、精神・感情について脳科学の知見にたって解説されていくのです。圧倒的な説得力ですよ。それと情報量がすごいです。発達障害について知識を深めたい方であれば、必ず知りたいことが解消されます。少なくともヒントはあります。
11月上旬探し求めていたもののヒントがみつかる
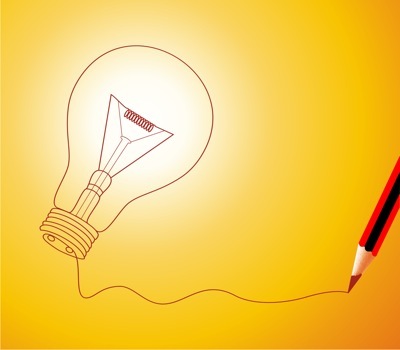
「活かそう!発達障害脳」P110
「発達障害の子の場合、情報処理の仕方に偏りがあるかもしれないので、それを見つけてあげて、得意な情報処理の仕方を伸ばせば弱い部分を補うことができるんです。それが治療なんです」
この部分ですね。これまで私の弱点を色々書いてきましたか
私の一番の問題点は「思考空白」にあると思っていました。ものを考えることもできない。ただ何か指示を与えられればそれに沿ってもの考えることができるのですが、それ以外では非常に難しいですね。これは何が原因というと、「認識できないことで外部の状況にアクセスできないこと」が原因だと思っていました。言うなれば窓のない部屋に閉じ込められている感じです。そのため、うまく物が考えられないことや、外部の状況に対応した思考を動かすことができないのではないか、と考えていました。
認識できない=外部との情報処理の仕方に問題があるではないかという事を考えていました。でも、どうすればいいかわからない。この状態が何十年も続いていましたが、この文章を読んで何がきっかけになるかもわからないそう感じたのでした。長沼先生に会いに行く事を決意しました。そして認識ができれば思考ができるかもしれない。そうすれば私の現状も変えること出来る。
26年1月下旬長沼医師1回目

北海道音更町の緑ヶ丘病院へいきました。結論から言うと、私の疑問「得意な情報処理の仕方」は解消されませんでした。そこまでの時間がなかったですね。聞くことが出来なかったです。診察の前に問診票への記入があるのですが、非常に多岐に渡っており、ここまで多角的にチェックをするのだと驚きました。そして、その後長時間にわたって非常に丁寧に説明をしてくださいました。かえって非常に申し訳ない気持ちです。
症状を緩和するためのいろいろな方法、代替療法も含めて非常に丁寧に説明して頂きました。
発達障害の治療ということがここまで進んでいるのかと驚きました。そしてさまざまなアプローチをしているのがよくわかりました。1つに自己啓発の分野では有名な「7つの習慣」という本があり、成功哲学、人生哲学、自助努力といった人間の生活を広く取り扱っているものです。その本を医師からまさか勧められるとは思わなかったです。医療的な治療といえば、まず服薬を考えると思っていましたから。ひとくちに発達障害と言っても、いろんなタイプの方がいて、それらに対処しようとするなら、それ相応の用意が必要なのだと思いました。
そして長沼医師についてです。明らかに私の持っている通常の医療の方のイメージとは違いました。説明の中で、「超感覚」と言われていますが、いわゆる超能力的なものが発達障害の感覚の中にあると思っていると感じました。そしてその「超感覚」を当事者が生きていく上でプラスと捉えて活かすという発想も持っている方でした。
余計なお世話ですが、正直周囲の医師や病院の理解を得られているのかと心配になるほどでした。大学の組織の中、病院という組織の中で患者さん本位の考え方をして、そのことを優先して準備をされている方がいるのだと、愕然としましたね。私は10年前に診断を受けたときとは違う。確実に進化している。確かに長沼医師のようなアプローチをする方は全国的に見て、多分少数派でしょう。それでも日本の医療の裾野の広がりに感動を覚えましたね。
そして、アスペルガーが社会で生きていくとどのようなことが起こるか。そういうことも説明していただきました。そういうところから、特徴の理解を促されているような印象です。そして私の特徴についても丁寧に話されています。以下の緑字は「活かそう発達障害脳」と長沼医師から頂いた資料からの引用です。
<マインズアイ>
イメージしたものを視覚化したり多角視したり操作できる能力です。実在するものを肉眼の目で見るのは一ボトムアップ信号」と呼ばれ、眼←後頭葉←イメージの内部表現の場所である側頭葉連合野←さらに海馬や前頭葉、という順番で情報が流れます。一方、イメージを創って見ることは「トップダウン信号」と呼ばれ、海馬や前頭葉‐←側頭葉連合野へと情報を逆に送り返します。
マインズ・アイというのは簡単にいえば、「目の前にないものが想像すれば見える」、「自分の頭の中のイメージが見える」っていうことなんです。僕は診療でよく使っているんですけど、見えている人には「え、みんなは見えないんですか?」と驚かれることがあります。そして、マインズ・アイがあるかないかでその人のある性質がわかってきます。
マインズ・アイで見るイメージは自分の中にあるイメージの内部表現を取りだしたものであり、目の前に肉眼で見えているのを取り入れたイメージではないんですね。そして、それだけではないことに気がつきました。自由に空間を移動でき、あらゆる視点を持てる不思議な目を持っている人もいるんです。例えば、目の前にあるガラス瓶の中に入って今いる部屋を見渡すこともできたりする人もいます。あるいは、頭上高く上がって自分を見下ろしてみることができたり。言い換えると、他者の視点になりきれる人、多次元的にものを見られる人たちなんです。どこにでも視点を持っていけて、しかも、ありありと思い描けるんです。だから周囲の事象を理解するにも、それを活かせばいいんですね。
<非言語性障害(NLD、non-verbal learning disorders)>
・一般的特徴
動作性IQが言語性IQより有意に低い
早期の会話や語彙発達
顕著な機械的記憶能力
細部への注意
早期の読字書字能力の発達
雄弁な自己表現
協調性運動の欠如
重度のバランス障害
巧綴性運動困難
イメージ(心像)の欠如や視覚的想起不全
空間認知障害
空間関係障害
非言語的コミュニケーション能力の欠如
変化や新規場面への適応困難
社会的判断や交流の重篤な欠陥
<HSP(Highly Sensitive Person)>
敏感で繊細、感受性が強く感じやすい人たちであり、おとなしい人に多いが、活発な人の中にもあり得る性質でもある。情報を半意識的または無意識的に処理してしまう直感的、第6感的・超感覚的な性質を持つとされ、人口の15から20%に見られる。感覚過敏性は自閉症スペクトラム障害の特徴の1つであるが、その他の発達障害特性を持つ人にもある。単なる感覚の敏感さというだけでなく、超感覚的な敏感さを併せ持つ。感覚過敏性は大人が意識してみたり聞いてりしないと見逃す可能性がある。敏感な神経を持つのは人間の正常な特徴の1つ。周囲に起こっている微妙なことを感じ取るという長所は、地域の強い環境に長時間いると真剣な圧倒されて、普通の人よりも疲れやすく動揺しやすいという短所でもある。
このhspという概念を使えば、私の改善点「他人の感情に影響されてしまう」、これが説明できてしまう。感覚的に分かってしまう。その人がどういう苦しみとか抱えているものが推測でなくわかってしまう。この感覚を他の人に言っても理解されくい部分がありますけどもそうなのです。
例えば、ある人が笑顔で明るく振る舞っていても、私には心の中で邪悪なこと考えていることが判ることがあります。私からしたら、本当に看板を掲げているようなものです。逆になぜ気がつかないの?
実際こういう特徴を私が持っていますが、この特徴を持っていて困ることがあります。感情に影響されてしまうこと以外でね。こういう認識というのは、言ってしまえば相互作用なのです。平たく言ってしまえば、私が気づいていることを他の人も気づいてしまう。
私と同じものを見るということではないですよ。私が何か違うもの見ていることに気づくのです。
例えば、私がcさんの背後に幽霊が見えるとします。幽霊のことが気になりますよね、ちらちら見てしまう。cさんは違和感を覚えます。そして、何回か続くと必ず気が付きます。「この人は何か違うものを見ている」と。テレビドラマなんかでよくあるパターンですが。そして霊感があることがばれてしまう。
結局のところ、人と違うことは隠せないのです。そして、また変わり者と言う噂がたてられてしまうのです。困ったものです。よくいろんな人に言われます、「あなたはなぜか知らないけど非常に目につく」。そういうことなのかなと思いますね。
私に似た人がいると初めて理解した

長沼医師から説明をして頂く中で、私の症状に合わせた資料を渡されました。それを参考にして説明をするというスタイルでした。ただ言葉での説明よりも頭に入りやすいし、再現性もあるので非常にありがたいです。
その中にある患者さんの資料がありました。生きてきて何を感じて、そしてその人なりにしてきた対応について書かれていました。長い文章ではなくA4,用紙2枚です。
それを読んで思わず涙が出てきました。そこに私がいたのでした。私が感じ、そして対応してきたことに非常に近いものでした。緑字引用です
「幼児期から現在まで周囲の世界になじめず居場所がなく親しい友人や家族関係が築けなかった。自分が理想とする友達を観察し分析し、どんな時にどんな言葉をどんな表情で出すべきかを細かくデータとして取り入れ蓄積して使ってきた。」
他の当時者も共感する人が多いと思う。私もそうなのでした。
まるで私の周りには壁があり私と世界を隔離されていると感じています。外の世界の人たちと私では見ているものが違う。そのため同じようなことを感じることができません。
でも、他人には私の感覚は分ってくれることは無理なのです。そうなると、私は自分を責めます。「なんで他の人と同じことができないのだ」と。自然には普通に振舞うことはできないのです。マニュアル操作的にならざるを得ません。ようするに状況に応じたセリフを「多分こうなのかな?」とビクビクしながら話すのです。薄氷の上を歩いているようなものです。
挨拶の感覚に近いかもわかりません。朝に出会ったらおはようございます。
天気が良かったら、いい天気ですね気持ちですね。そんなことちっとも思ってないですけどね。子供がいたら可愛いですね、花を見かけたら美しいですね。そこには何の感情もなく共感もありません。ただ生き延びるために、他人から「何か違う」と思われないために、ただ自分の用意したスイッチを押しているだけ。こんなことを長年していると、だんだん心が麻痺してくる。この文章読んだ時、過去の記憶が蘇ったね。
「人の感情に左右されやすく、人の心の動きが詳細に感じられ感情を生々しく感じることがあり、人の多くいるところだと様々な感情が次々と押し寄せてきて疲れたり気分が落ち込んだりした」
なぜ人は人の心に影響されないのだろう。決して洞察力があるというわけではないです。ただその人の悲しみとか怒りとかそういうその人の感情がただ解ってしまう。赤色を見たら赤色と思いますよね。黒色を見たら黒色ですね。そこに何か違う要素が入る余地がないです。そしてただ判ってしまし、影響をうけてしまう。
この文章見たとき私はで衝撃的でしたね。心が揺れました。自分の過去の思い出がオーバーラップしてきました。それと別に一緒の感動が私を包みました。私のほかに私と似ている感覚の人間が居るのだ。深い感動でした。
1回目の受診後、帰り道

帰り道、色んな事思いました。自分と同じような悩みを持っている人がいるということが理解できました。そのことだけでも、長沼先生に会いに来た価値があるなと思いましたね。
私の疑問の答えはまだわからないですが、それでもです。
文章にして発表しよう。そう決意しました。何をかというと、これまで私がどう発達障害の症状を軽減してきたかを、です。多分その意義はあると思う。発達障害者の症状は人それぞれだとよく言われることがありますが、それでも私に似たような人がいるのであれば、たぶん意味があるのだと思う。全部じゃなくてもいいのだ。少しでも参考になる部分があれば意味がある。
この時思ったのが互助の精神です。多分それぞれの当事者の知恵を持ちよれば、データベースみたいのものができるじゃないかな。そのことによって救われる当事者がいるかもしれない。データベースのようなものが、まだ出来ていないのならば、書く事で何かの呼び水になるかもわからない。
これまでの経験のことを考えました。障害年金受給の事だったり、「置口空助」を頂いたことだったり、ささやき声だったり、追われるように辞めていったことを。文章を書くなら今この時期しかない。今、無職の状態でいるのはラッキーなことだね。文章書くことに集中できる。このことに感謝しなくちゃいけないね。
ばらばらだった、パズルのピースが嵌った感覚ですね。そして書かなかったら多分、私は日本一の馬鹿野郎ですよ。書くことでこの10年の総決算とする。書いて次の10年に行く。そう決めたのでした。リミットは平成26年9月12日です。
帰宅後

まず緑ヶ丘病院に予約の電話いれました。次回こそは「得意な情報処理の仕方」のことを聞くためです。そして、受診までに自分の考えをまとめて事前に郵送しようと考えました。長沼医師に、あまり時間をとらせるわけにはいかない。
帰宅後非常に感覚が敏感になっていました。相手の感情が鋭敏にわかるようになりました
それどころかもの残っている残留思念を感じ取れるような感じです。あくまでも私個人の意見ですよ。体全体がアンテナのようになった感じですね。
2月11日(多分)のことです。その日は体調も良好でした。いつものようにすべき作業をしていると、あることに気がつきました。私の中に私がいました。もちろんイメージですよ。イメージの中で私が私の中を覗き込む感じ。これも理解してくれる人は少ないかもわからない。
どう説明したらいいのだろ。自分の中に自分がいる。人によっては幻覚という形で理解する人もいるのかな。リアル過ぎる程、視覚的ものでした。もちろんイメージなのでしょうけども。ぱっちり目が合いましたもんね。彼はシマシマのスエット着ていました。そして、恥ずかしそうに笑っていました。
一瞬「なんだお前」と思いましたが、理解しました。
「これは私だ」
「別人格ではないな。俺自身がそこにいる。困った顔でそこに立っている」
私の部屋に立っているというわけではないです。私の中にいる感じです。
記憶が蘇る

そしてここでいろんな記憶が蘇ってきました。私の中に私を見つけた事はこれまで何回もあったのでした。最初の記憶は多分平成19年頃です。それから数度多分3・4回は同じようなことが起きていました。そして、「かつて、私はもう一人の自分に気がついていた」と繰り返し思うのです。そして、そのことを忘れるのです。原因は「思考がとぶ」ですね。この状態なると記憶も相当持ってかれてしまう。そして「思考がとぶ」この状態は私の中の私、彼と呼びます。彼の影響が強い状態なのだと理解しました。このことも繰り返しですが(笑)。
私が何を考えどうゆう気持ちで発達障害の克服ということに取り組んできた か。
今このストーリーで色々書いていますけども、この時によみがえった記憶を元に書いています。試行錯誤をしながら、自分のできることを広げてきたのでした。
そして、大事なこと思い出します。彼に気がついた私は。かつてコンタクトを取ろうと何度も会話を試みました。非常に彼は苦しんでいます。疲労困憊しているといってもいいでしょう。苦しんでいる彼にかける言葉はなかった。どうして良いか判らなかったのです。
私が斎藤一人さんの「100回聞きCD」にこだわる理由が理解できました。彼とコンタクトを取る手段として「100回聞きCD」を使おうと思ったのでした。なぜならそこには人生を生きるための知恵が詰まっており、「100回聞きCD」ならば、苦しんでいる彼とそれを助けることが出来ると思ったのです。特に私に対して、害を及ぼすとかそういう印象なかったですね。ただひたすら苦しんいでる。
多分私のマイナスの感情を一手に引き受けてくれている存在なのかと。であるならば、ここで誓います。必ず楽にします。
その後、彼の影響が非常に強くなりましたね。わたしもコントロール不能に近い感じでしたね。
実際何が起こったかというと。過食に走るのです。でも、ギャンブルや犯罪的なものに走るじゃなくてよかったよ。
ストレスが溜まると過食に走る。これも私の要求と言うよりは、彼のストレス軽減のために彼が食べていることを理解しました。弱点「過食」の意味を理解したのでした。
「消費者金融でお金を借りて、全部食べちゃったってこともあったけどそれもお前か」。行き場のない怒りも少しは感じましたが(笑)。でもいいよ、許す。
25年2月下旬長沼医師2回目

「得意な情報処理の仕方」、このことに関しては明確な説明はなかったです。多分私の考えているものと、先生と考える「情報処理」が違うのかなと思いました。捉え方が違う。自分の狭い知識と感覚で考えている人間と、医師とではその定義自体がおそらく違うということかな。ただ、先生との会話の中で色んなアプローチの方法を思いつきました。
彼のことも相談しました。先生からは「多分それは解離性障害ということで説明ができると思います」と説明をしていただきました。私の弱点「思考が飛ぶ」、これはある種の精神疾患なのでした。そして発達障害者のかなりの割合の方が、解離性障害をもつということも判りました。わたしの場合は小学校からですので、その頃非常に強いストレスを感じていたということです。どれだけ、ただ生きることが辛かったんだろうね。
現在解離に対しての投薬以外の治療法ついて質問をしました。このときすでに斉藤一人さんの教えでもって対抗すると決めていましたので、参考にしたかったのです。ある本を紹介されました。いまのところ最先端に近いものだということでした。言葉を使って解離を解消するというものでした。アプローチとしては私の考えているものと同じでした。正直勇気付けられましたね。少なくとも間違っていないということですから。待っていろよ、必ず「彼」を救う。
厚生労働省のホームページから
私たちの記憶や意識、知覚やアイデンティティ(自我同一性)は本来1つにまとまっています。解離とは、これらの感覚をまとめる能力が一時的に失われた状態です。たとえば、過去の記憶の一部が抜け落ちたり、知覚の一部を感じなくなったり、感情が麻痺するといったことが起こります。ただ、解離状態においては通常は体験されない知覚や行動が新たに出現することもあります。異常行動(とん走そのほか)や、新たな人格の形成(多重人格障害、シャーマニズムなど)は代表的な例です。これらの解離現象は、軽くて一時的なものであれば、健康な人に現れることもあります。
こうした症状が深刻で、日常の生活に支障をきたすような状態を解離性障害といいます。原因としては、ストレスや心的外傷が関係しているといわれます。この心的外傷には様々な種類があります。災害、事故、暴行を受けるなど一過性のものもあれば、性的虐待、長期にわたる監禁状態や戦闘体験など慢性的に何度もくりかえされるものもあります。
そのようなつらい体験によるダメージを避けるため、精神が緊急避難的に機能の一部を停止させることが解離性障害につながると考えられています。

